
営業が怖くて、なかなか一歩が踏み出せない…
めっちゃ分かります。
なんせ僕だってWeb制作も営業も未経験のくせに、完全独学で身につけたコーディングだけを武器にして営業っぽいことをはじめた身の程知らずのひとりだったので。笑
しかし、あれから5年。
気がつけばフリーランスのWebディレクター/マーケターとしてお仕事を任せていただく一方で、メンターとして、Web制作のフリーランスを目指す方々の独学・営業・案件対応を個別にサポートする日々を送るまでになりました。
今回は、そんな僕の実体験とメンター活動を通じて確信した「稼げるフリーランス」になるリアルなノウハウを5本の記事で完全解説します!
5本すべて読んでくれた方には「読者限定特典」があります!
詳細は5本目の記事の最後をご確認ください。
「制作会社のパートナー」「ココナラで自動集客」「エンド向けにとことん営業」などなど、Web制作で稼ぐにも方法は様々。
しかし、どの道を選ぶにしても必ず準備しておかなければならないことがあるってご存知ですか?
その準備を1週間ほどで整えられる人もいれば、1ヶ月は必要な人もいるでしょうけど、完全独学だった僕は1年以上掛かってしまいました。
僕が迷子になっていた頃って、デイトラもなければこういう記事もなかったですからね。
ということで、「一生懸命がんばってスキルは身につけたのに全然案件を獲得できてない人」や「営業がとにかく怖い人」は今すぐこの記事をお気に入りに登録して、①から順番に何度も読んでください!
過去最大のボリュームになっていますが、その分、下手な有料コンテンツよりも遥かに詳しく解説しています。
何度も言いますが、ぜひこの記事を繰り返し読んでいただき、必ずや月に50万円でも100万円でも「稼ぎ続けるフリーランス」になりましょう!
- 3つの前提確認 ←本記事はこちら
- 起業前の基盤づくり
- 信頼の築き方
- 価格設定と営業方法
- 認知獲得のための7大戦略
本記事の目次はコチラ↓
本記事の目次
はじめに
本記事の目的〜2.0を執筆するにあたり
2022年に書いた『案件獲得ロードマップ』。
Web制作でフリーランスを目指す2万人以上の方々に読んでいただき、気がつけば『独学応援ロードマップ』に次ぐ当ブログの看板記事となりました。
そんな『案件獲得ロードマップ』に書いたのは以下の4点。
- フリーランスとして理解しておくべき大前提
- Web制作における仕事の種類
- 案件獲得に必要なこと・もの
- 営業の基本
これらの内容は今でも通用するものですし、特に①②はこれから案件獲得に向けて営業をはじめるすべての方に読んでおいてほしい内容でした。
ここを理解できてないと0→1すら難しいのですからね。
一方で、ぶっちゃけ物足りなさを感じたのが③④。
③④はその内容の補足・深掘りをBrainという形で別記事に委ねていましたが、それにしてももう少し詳しく書いてもいいんじゃね?と我ながら思ったわけです。
ということで、これから書こうとしている『案件獲得ロードマップ 2.0』では①②の内容はそのままに、③④の内容をより詳しく具体的にすることを目的とします。
つまり、『案件獲得ロードマップ 2.0』を徹底的に参考にしていただくと、営業未経験の方でも「フリーランスとして仕事の絶えない状態を目指すために必要な準備」について順を追って具体的に学び、準備できるようになります。
それも無料で。
結構すごそうな記事になる気がしませんか?
読者の感想
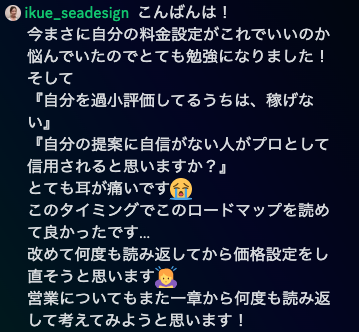
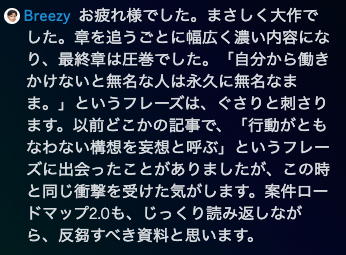
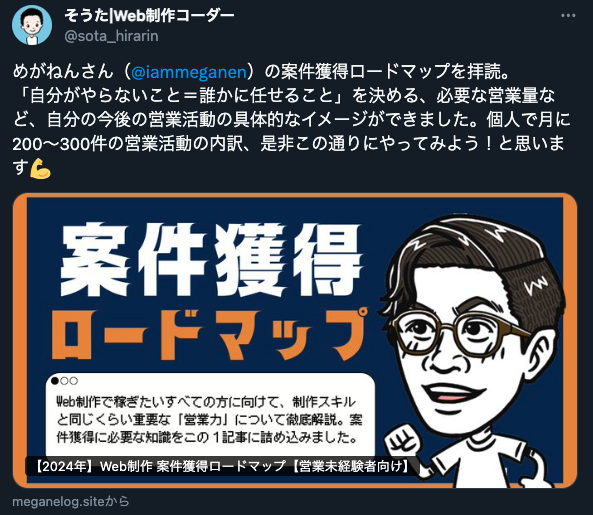
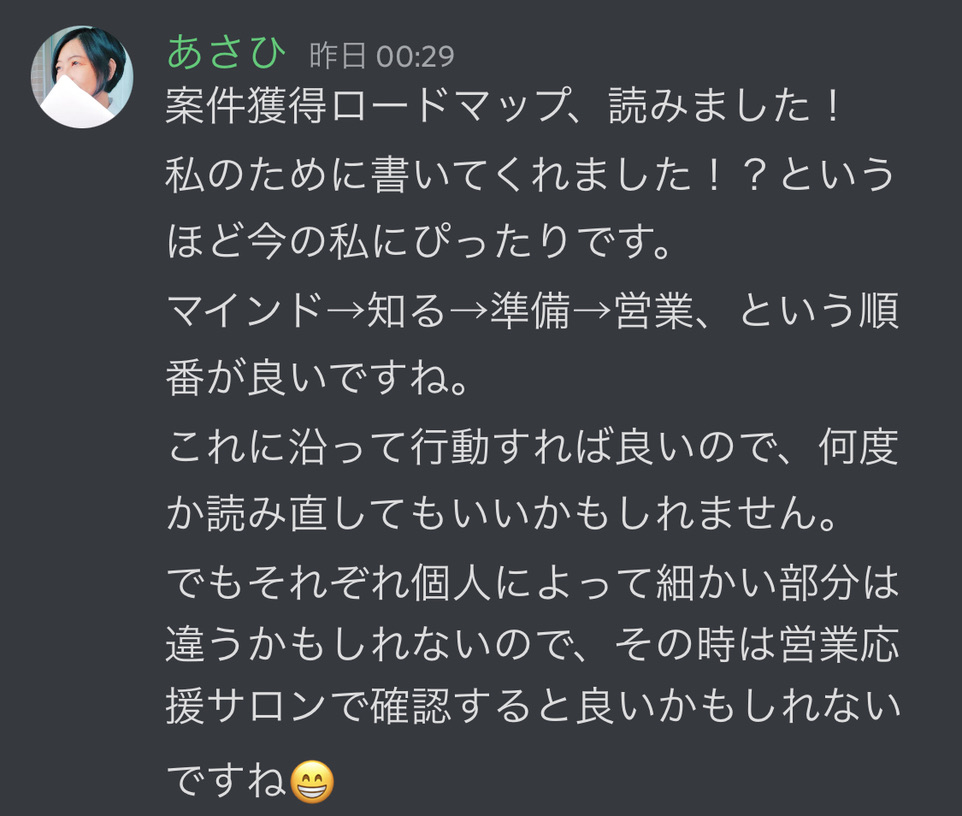

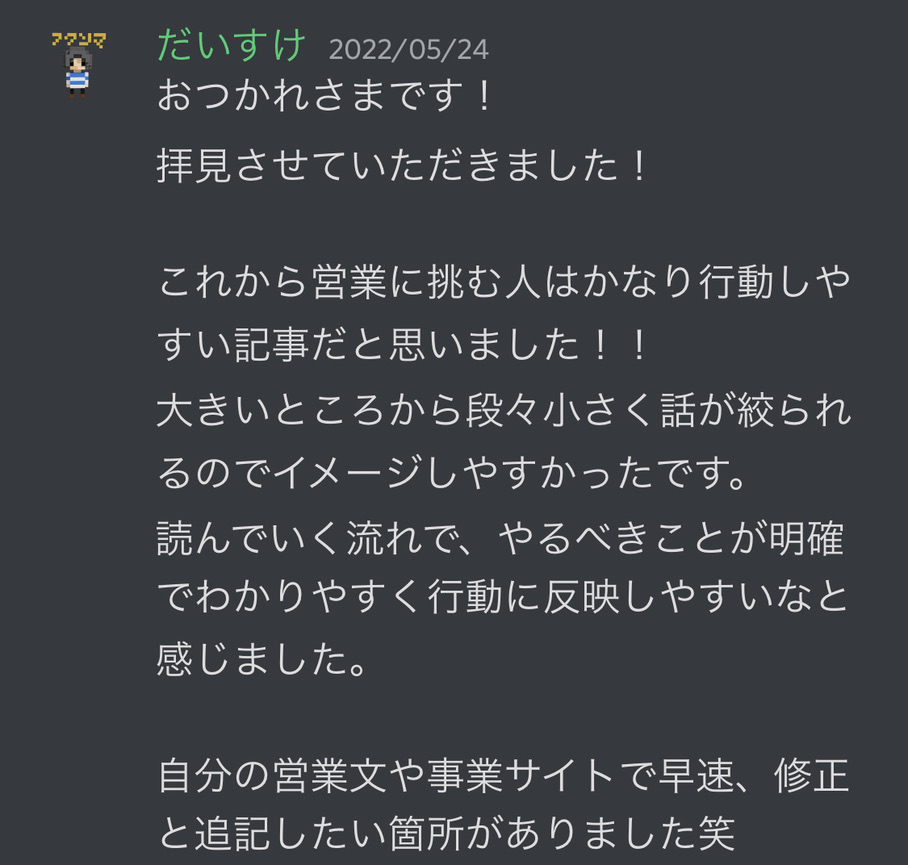
それでは、いよいよ解説のはじまりです!
1本目となるこの記事では、「稼げるフリーランス」を目指すために知っておくべき「前提」となる3つの知識を解説。
実際の営業準備に取り掛かる前に、まずはこの記事で必要な知識をチェックしておきましょう!
【前提1】フリーランスとして生き抜くために意識してほしい姿勢

案件獲得に向けた準備に取り掛かる前に、まずは意識すべき姿勢を確認しておきましょう。
ずばり「フリーランスとして生き抜くために意識してほしい姿勢」は下記の5つ。
- とにかく行動する
- やらないことを決める
- 教材やアドバイスを素直に再現する
- 仕事を引き受けたら、価格以上の働きで応える
- 自己投資は積極的に行う
①とにかく行動する
情報がとっくに民主化された今、最も大切なことは手にした情報を活用するためにとことん行動すること。
ヒット率の低さは気にせず、とにかく打席に何度も立ち続けてください!
5つある大切な姿勢の中でも、いちばん重要なのがこれ。
フリーランスとして成功するための絶対条件です。
当然スキルを磨いたり、顧客像をイメージするなどといった準備も必要ですが、そうした必要な準備を行ったのならあとは行動あるのみ。
行動し続けなくては、失敗すらできませんからね。
「必要な準備」についてはこの記事で解説していますので、それさえ終わればあとはトライアンドエラーの連続ですし、それを楽しめるマインドが肝要です。
②やらないことを決める
断言します。
「Web制作を自分一人でやりきるために準備しています!」っていう人は、99%準備中に挫折します。
そんなの、家を建てようとして木材の手配から施工までを自分一人でやろうとするくらい無謀ですからね。
まずはWeb制作の各工程を理解し、その中で自分が担う役割とそうでない役割を明確にしましょう!
◆営業
・相談/簡易説明
・詳細ヒアリング
・提案
・受注
◆ディレクション
・日程調整
・メンバー確定
・ワイヤー作成
・合意形成
◆デザイン
・トップページ デザイン作成
・下層ページ デザイン作成
・合意形成
◆コーディング
・コーディング
・合意形成
・テスト公開
・合意形成
こうすることで「自分が集中すべきこと」が明確になり、これに集中して経験を積むことで最終的には「お客様に約束できること」がハッキリします。
この「お客様に約束できること」がハッキリしていないと誰だって営業できないですし、案件獲得も不可能ですから、「やらないこと決める」というのはとても重要な準備なんです。
僕の場合は「デザインはやらない」と決めていたので、今日に至るまで自分でデザインしたことは一度もありません。初案件からずっと外注してきました。
初心者なら最初の案件は利益をすべて外注費として振り込んでパートナーに「良い仕事」をしてもらう方が、自分ですべてを担当するために何年も学習するより遥かに時間もお金も節約できますし、クライアントやパートナーとの良好な関係構築にもつなげられます。
その分、早い段階で制作体制が整って営業にも踏み切れますよね。
あなたは何をやりませんか?
③教材やアドバイスを素直に再現する
会社員として後輩の育成も行ってきた僕ですが、成長が遅いだけでなく、後々「悪い先輩」になってしまった人たちは、決まって新人の頃から素直じゃありませんでした。
こちらのアドバイスに対して「いや、でも…」と自分の言動を肯定することから話しはじめてしまうので、結果的に自分の過ちを受け入れられず、改善もできなかったわけです。
Web制作の初学者にも同じことが言えます。
逆にこちらのアドバイスを素直に聞き入れてもらえると、アドバイスした側としては余計に応援したくなりますし、それで失敗してしまった場合は全力でサポートしたくなるもの。
それは結果的に人脈を広げることができますし、そもそも経験者の成功方法を追体験することで確実に成長できるので、一切の無駄がないわけです。
相談したなら、まずはその通りに実行してみる。かなり大切です。
④仕事を引き受けたら、価格以上の働きで応える
出世する会社員が「給料の3倍以上の仕事」をしているように、仕事が絶えないフリーランスは「価格以上の価値」を提供しています。
たまに「給料以上の仕事はしたくない」なんて人もいますが、そもそも「給料以内の仕事」とは「上司やクライアントの期待通りの仕事」ですから、「給料以上の仕事をしないと上司は驚きも感激もせず給料を上げてあげなきゃとは思えない」わけです。
ということで、フリーランスを目指すなら「価格以上の価値」を提供することに全集中してもらいたいところ。
Web制作でフリーランスを目指すなら「求められているものを作れる」というのは当たり前なので、それに上乗せできる何かがとても重要になってきます。
その「何か」といえば、実績が少ないうちだと「即レス」「こまめな報連相」「納期の徹底厳守」など。
いずれにしても、価格以上の価値を提供し、あなたと仕事をしていきたいと感じてもらえる関係性を築くことを目指しましょう。
誰がなんというと、仕事は人脈命ですからね。
「即レス」を誤解している人が多いので、ここで補足しておきますね。
「即レス」と「即答」は違います。
「即レス」の「レス」はレスポンス、つまり「反応すること」です。
即答できれば一番良いですが、すぐに答えられないのであれば「確認して12時までにお返事させていただきます。お待たせしてしまい恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。」と返せばいいんです。
スマホで「かか」と打ったら、「確認して12時までにお返事させていただきます。お待たせしてしまい恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。」と変換されるようにしておけば、時間のとこなどを編集して送信するだけ。
1分もあれば余裕でしょう。
僕は会社のトイレや駅のホームで必死に返信していましたが、ちょっとした工夫で即レスは誰でもできますし、徹底することで相手に安心してもらえるのでコスパも最高です。
⑤自己投資は積極的に行う
基本的にパソコンのスペックが、あなたの作業効率の限界です。
基本的にしょぼいパソコンではしょぼい仕事しかできません。
「弘法筆を選ばず」とか言いますが、弘法大師ではないあなたは一旦忘れてください。
また、フリーランスとして活動する上で知識をアップデートし続けることはとても大切です。
知らないことは提供できないですからね。
したがって、教材についても「必要性を感じたときには一切ケチらずその場で買う」というのを自分ルールとして明確に自分に課しておいてください。
さらに、X(Twitter)などで誰が無料で配ってくれた資料などを受け取ったら、それらはその日のうちに読み切りたいところ。
無料だからといってもらうだけもらって読んでないというのは、非常にもったいないと思いませんか?
受け取る→読む→感想をポスト(ツイート)する、これだけで知識が増える上に制作者やそのフォロワーとも繋がれるチャンスを得られるので、ぜひとも無駄にしないようにしましょう。
【前提2】仕事の種類を知る

姿勢を確認できたところで、お次はいよいよ営業先について。
営業先によって求められるスキルや力量も異なりますので、当ブログでは独学前に調べておくべきポイントとしてお伝えしている「仕事の種類」。
この記事から当ブログを読みはじめてくださっている方の中には「そんな知らない!」という方もいるでしょうから、フリーランスとして仕事をしていく上で考えられる代表的な営業先を確認しておきましょう。
- 求人サイト
- クラウドソーシング
- 制作会社
- エンド営業
- 同業者
求人サイト
誰でも登録しておくだけで希望に近い案件に出会えるようになる「求人サイト」。
単価も仕事内容も様々ですが、「自分からガツガツ営業できない方」や「副業で続けたい方」はとりあえず登録だけしておいて、定期的に案件一覧を確認するようにしましょう。
稀に未経験採用で高待遇の求人が出てくることもありますので、転職を検討している方には特に最優先で登録とプロフィールの作り込みをおすすめします。
とりあえず無料登録しておいて、求人内容をチェックしておきましょう。
クラウドソーシング
「副業/フリーランスといえば」というくらい定番の案件獲得先となっているクラウドソーシング。
たしかに、初心者にとっては一番営業しやすい環境です。
代表的なものは下記の4つ。
で、これらに共通していえるのは基本的に「単価が低い」ということ。
というのも、クラウドソーシングで発注する方というのは「相場感を知らない」「自分で作れない」「予算が少なくて制作会社に発注できない」というケースがほとんど。
もちろん圧倒的な技術力で引っ張りだこの凄腕フリーランスもいますが、未経験のあなたがそこを狙うのは100万年後の話。
初心者がクラウドソーシングを利用するときは、お金を稼ぐためではなく、今後の営業に向けて実績を積むことに集中しましょう。
未経験でもココナラやランサーズで営業を自動化できるのは事実ですが、とはいえ駆け出した最初の段階で多くの方が提供できるスキルはコーディングかデザインといった単一スキルだけのはず。
単一のスキルだけでは案件数も少ない上に、のちのち実績として掲載できなさそうな案件も少ないでしょう。
前述のとおり、Webに詳しくない人はディレクションもデザインも全部まとめてお願いしたくてクラウドソーシングに求人を出しているわけですから、そうしたニーズを考えると、ビジネスの原理原則(詳しくは次の章で解説してます)すら理解していない状態では苦戦を強いられることがご理解いただけるのではないでしょうか?
じゃあ、コーディングスキルしかない上にディレクションなどを外注できる人も知らない…という方はどうすべきなのか?
ということで、制作会社営業の説明です。
📢 「受注だけでなく、ポートフォリオも営業も最適化したいあなたへ!」
🎯 通常18,000円 → 今だけ15,000円!
📦 セット内容:
✅ 【完全版】クラウドソーシングの提案文テンプレ(10,000円)
✅ 案件獲得につながるポートフォリオ講座(3,000円)
✅ 紹介 & リピートを生み出す営業術講座(5,000円)
⏬ 【営業未経験OK】クラウドソーシングで希望単価を獲得する受注戦略|3つのコンテンツをまとめました
制作会社

結論、複数の制作会社とパートナー契約を結べて、毎月お仕事が絶えない状態を作れたら、月に60万円は稼げるはずです。フリーランスとして独立できちゃいます。
ということで、制作会社に営業しましょう。
必要なのは「実力」と「営業力」。
デザインを正確に再現できるコーディング力(もしくはクライアントの目的を理解したデザイン力)があり、その上で潜在顧客に相手の課題を自分がどう解決できるのか?を説明するためのチャンスをもらえる営業力があれば、あとはご縁とタイミングの問題です。
コーディング力は勉強すれば誰だって身につけられますね。
営業時に伝えたい自分の強みなどはポートフォリオを作った段階で言語化できてるはずですので、ポートフォリオの構成を上から順番に思い出すだけ。
あとは、勇気を出して営業に踏み切りましょう。
営業方法については次回以降で詳しく解説していますが、それを学んだ上で月に300〜500件くらい営業して返信が1件もないということであれば、僕にDMでご相談ください。
エンド営業
WSSクラスの登場で、一気に多くの方が挑戦するようになったエンド営業。
メールなり、テレアポなり、飛び込みなりで直接営業をかけていき、仕事につなげるわけですね。
法人との仕事になるので基本的に高単価でして、営業上手な方は個人でもホームページ制作を200万円で受注したりしています。
ここで求められるのは、当然どんなホームページを作れるのか?ということよりも、あなたに任せることでどれくらい売上や集客力が向上するのか?ということ。
つまり、ビジネスモデルの構築やマーケティング、Webサイトの分析や改善などといった知識が必要になってきます。
これらの知識はどれも独学で学べるものですが、習得までに1年以上の時間が必要。
当ブログでもノウハウや教材を紹介していますし、質問いただければいつでも学習方法をお伝えしますが、裏を返せばそれだけ準備が必要なので営業初心者の方にはおすすめしません。
営業手法の学習はもちろん、しっかり実績を積みながら自分でブログなどを運営してWebマーケティングやサイトの分析・改善の知識も身につけていきましょう。
※エンド営業の正しいやり方について独学で学ぶ場合は、WSSクラス代表のそうたさんが書いたこちらの教材が一番詳しいです。
エンド営業の手法のひとつに、ビジネスマッチングアプリである《Yenta》を使うという手段もあります。
僕は3ヶ月だけ月額5,000円くらいの有料プランを使用し、その期間中に肩書を「経営者」や「代表」「税理士」とされている方だけが候補として表示されるように設定して、ひたすら右にスワイプしてました。
その後は無料プランに戻しましたが、結果的にこのときの活動がキッカケで法人のSNS運用のサポートやSNSコンサル企業の業務代行などを任せていただいたり、経営者同士が集まるクローズドなコミュニティに招待していただけたので、「エンド営業の自動化」を目指したい方には非常におすすめです。
同業者
最後に紹介するのが、同業者に対する営業。
あなたがコーダーならば、Webデザイナーの方にアプローチするということです。
多くのWebデザイナーは自分でもコーディングできますが、できることならコーディングは外注したがっている方が多いので、そこの需要に応えるというもの。
その逆もまた然り。
このパターンの成功事例としては、ここあさんのココナラチャレンジなどが有名ですね。
これはマインドのところで話した「やらないことを決める」にも通ずることですが、つまりはあなたが「やらないと決めたこと=できないこと」を任せられる人とつながることで、「できるチーム」を作り上げ、自分たちの提案の幅を広げるわけです。
こうなると、あなたも相手も営業力が増す上に、どちらかが営業に成功すればお互いに稼げるという関係性にも発展しますし。制作会社に対しても制作体制が整っていることを説明できるので、より営業しやすくなります。
こうした協業できる相手を複数人作っておくことも、重要な人脈形成のひとつです。
営業をはじめる前にキャッシュフローのことも考えてください。
特に懸念しておくべきなのが「制作費の未払い」。
僕も駆け出し当時にTwitterでご依頼いただいたLP案件の制作費が未払いのままクライアントに逃げられたり、外注相手が音信不通になって制作会社から責任を問われたりと困ったことが何度かありました。
制作会社が約束の日付までに制作費を支払ってくれないことも珍しくありません。
そういうときに、フリーランスのことを守ってくれる保険が《フリーナンス》。
無料で損害賠償補償を受けられる上に、Lancersなどで即日払いも利用できるサービスです。
少ない元手で営業をはじめる方は、万が一に備えて必ず加入されることをおすすめします。
【前提3】ビジネスの大原則

ここまでで実際の仕事のイメージを掴めたら、最後に社会人として絶対に理解しておいてほしい「ビジネスの大原則」である4ステップを確認しておきましょう。
当たり前すぎる話ではありますが、ここを理解できてさえいればこのあとの解説の理解度もグッと高まりますのでぜひご確認ください。
ビジネスの4大原則
- 認知
- 興味・関心
- 販売
- リピート
どんな業種であれ、この4ステップを無視することはできません。
高卒底辺サラリーマンだった僕は『ビジネスモデルマスター講座』で勉強するまでこの基本すら知りませんでしたが、みなさんは営業活動に乗り出す前にこの記事でしっかりと理解して、僕みたいに恥を掻かないようにしておきましょう。
ということで、もう少し具体的に説明します。
まずはじめに商品・サービスの存在に気づいてもらい(認知)、
その特徴やメリットを想像してもらい(興味・関心)、
購入してもらい(販売)、
そのクオリティに満足してもらうことで使い続けてもらう(リピート)。
この流れを順番・順調に踏んでいくことがビジネスを成功させるための大原則であり、これを逆から準備していくことが、ビジネスを成功させるために必要なステップとなります。
つまり、
まずはじめは、将来的に「リピート」してもらえるくらい質の高い商品・サービスの開発に努めます。
その商品・サービスを「販売」するために、お客さまがそれを利用した際に生じるベネフィットをできるかぎり具体的にイメージしてもらえる説明や、納得できる価格設定を用意します。
用意した説明や価格を伝えて「興味・関心」を持ってもらうために、それらを確認できる資料やWebサイトを制作します。
最後に、それらの存在を「認知」してもらうために営業します。
ここまでをご理解いただいた上で実際の営業準備に取り掛かってもらえると、これからの自分の行動の意味がハッキリするのでモチベーションの低下なども防げるようになりますし、営業活動が迷走したときにこの基本に立ち返ることで改善策を考えやすくなるんです。
ぜひ、ここの理解を大切にしていただければと思います。
ということで、次章からはいよいよ稼げるフリーランスになるための本格的な準備をはじめていきましょう!
突然ですが、質問です。
「フリーランスとして稼ぐにあたって一番最初に決めるべきこと」はなんだと思いますか?
この記事の続きはこちら
【保存版】Web制作 案件獲得ロードマップ 2.0【②起業前の基盤づくり】
この記事が独学をがんばる皆さんのお役に立てたらうれしいです。
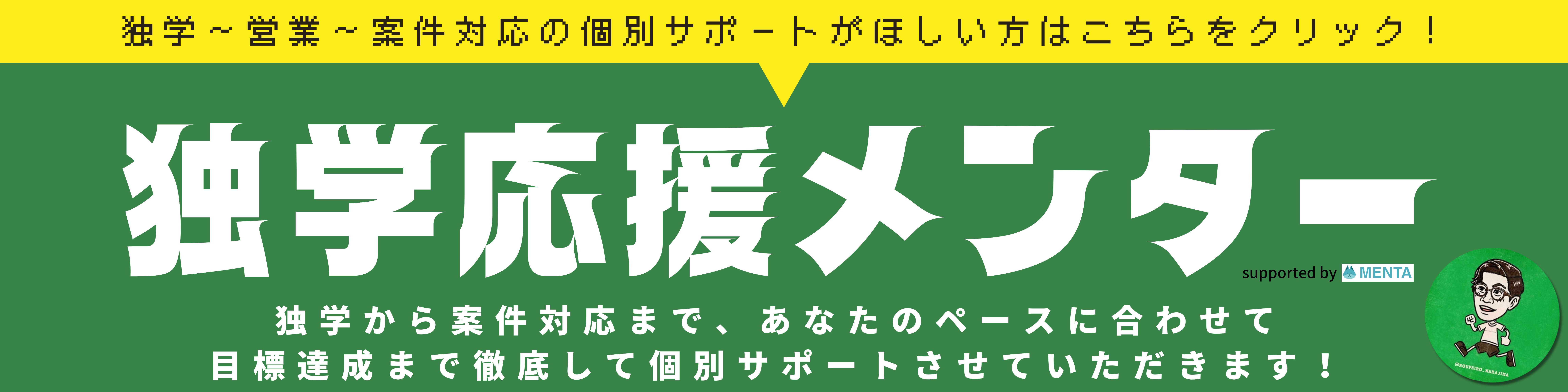
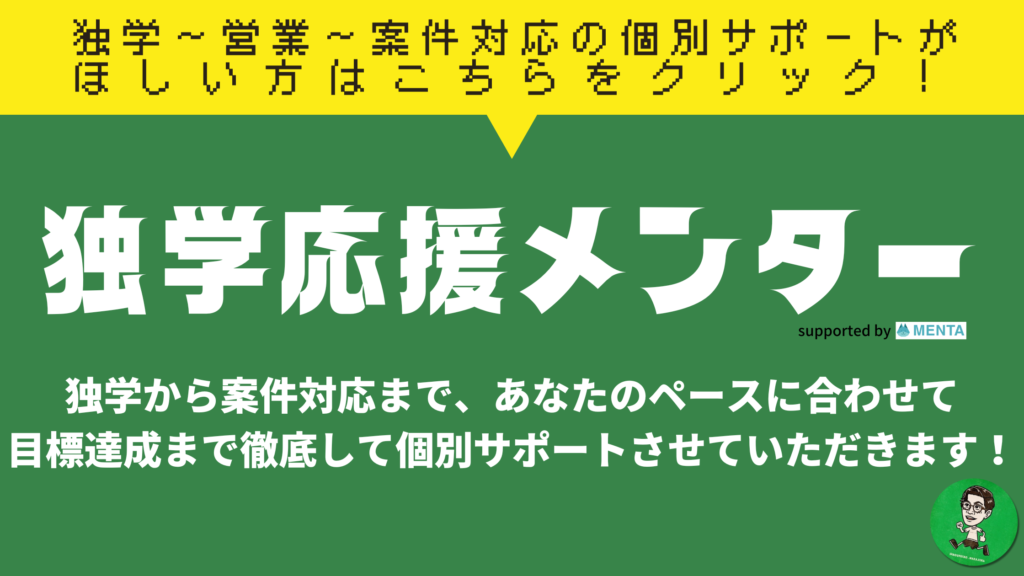
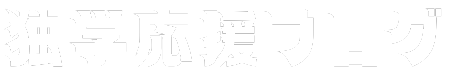
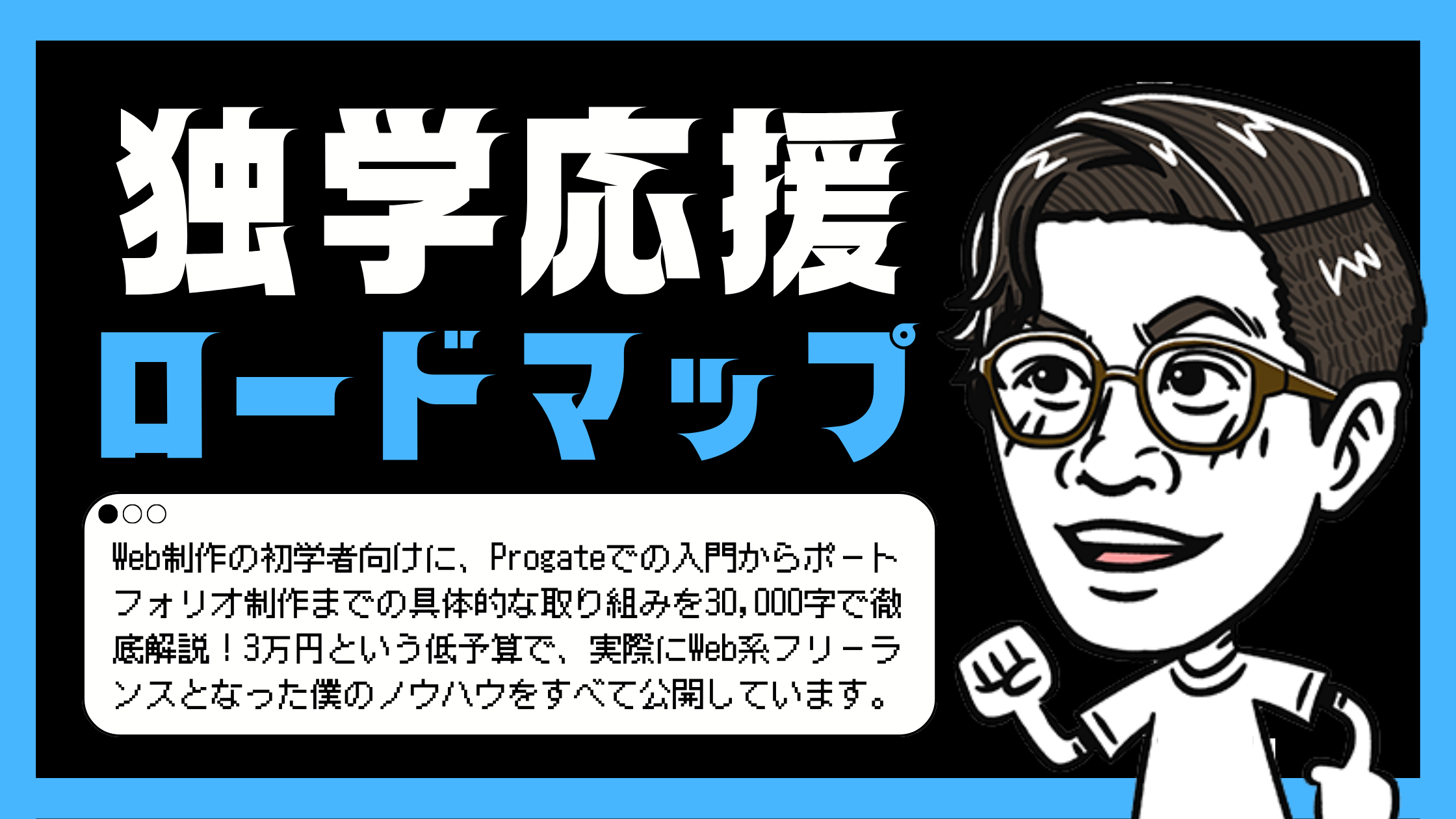

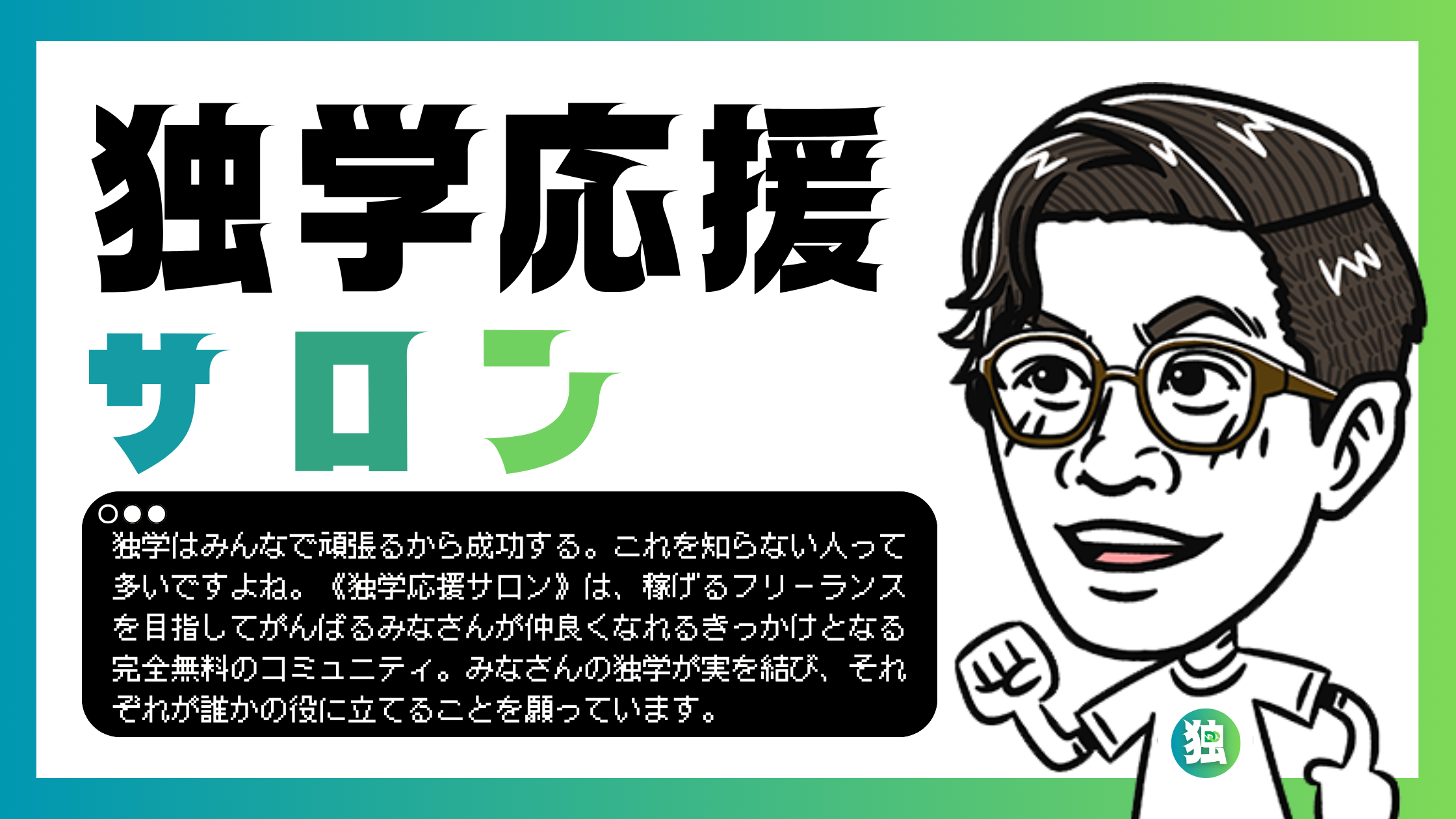


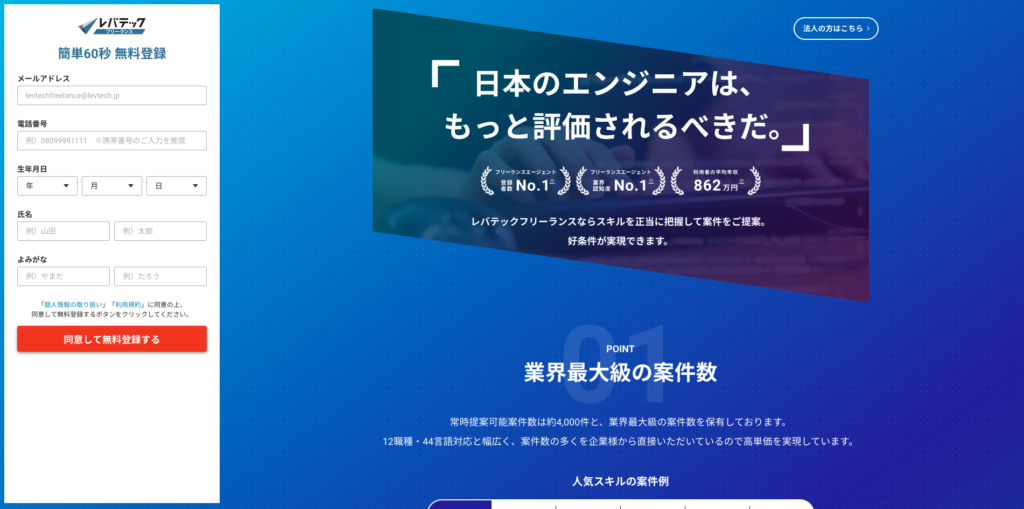







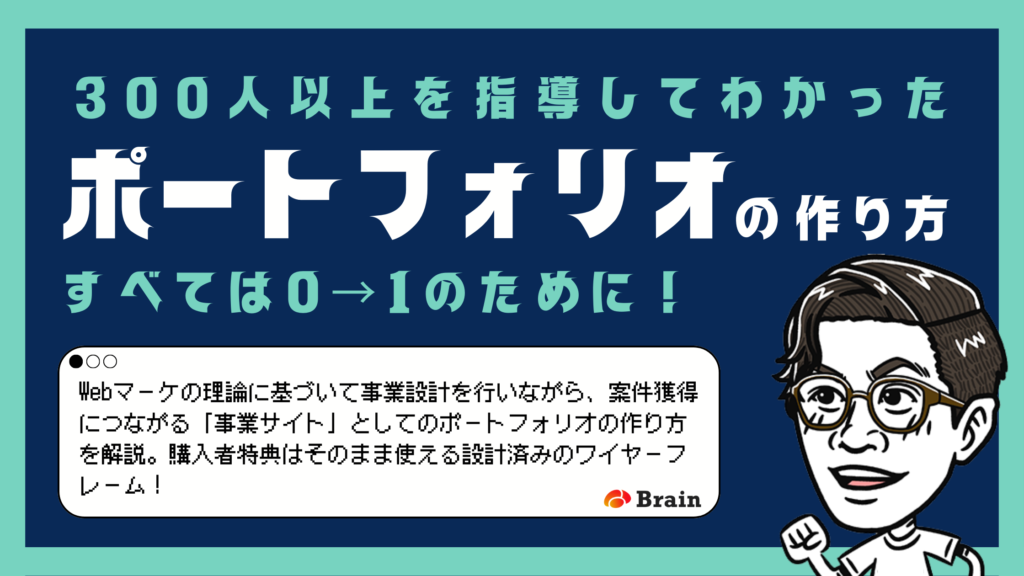


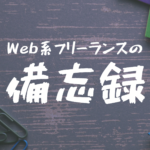
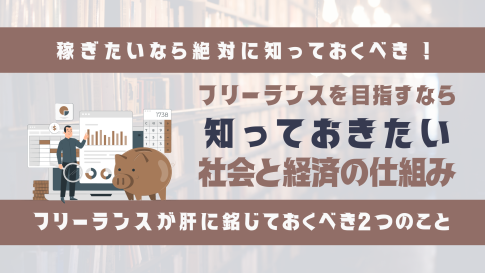
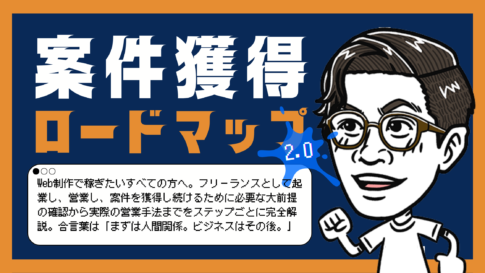
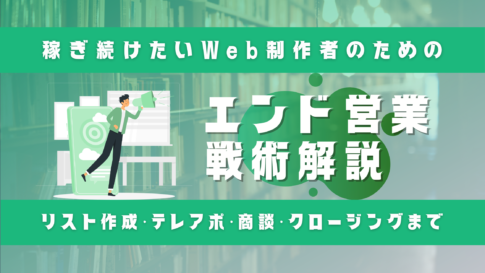
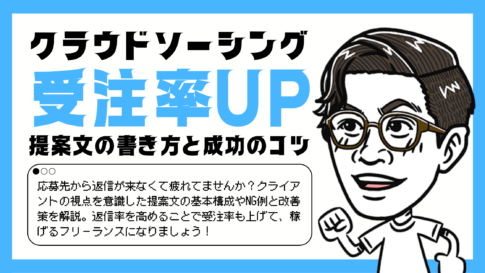

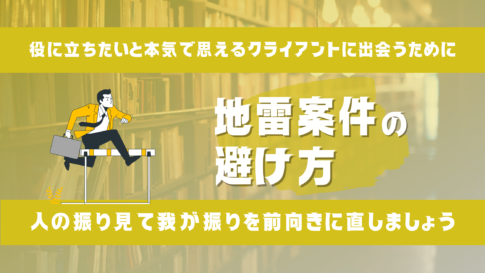

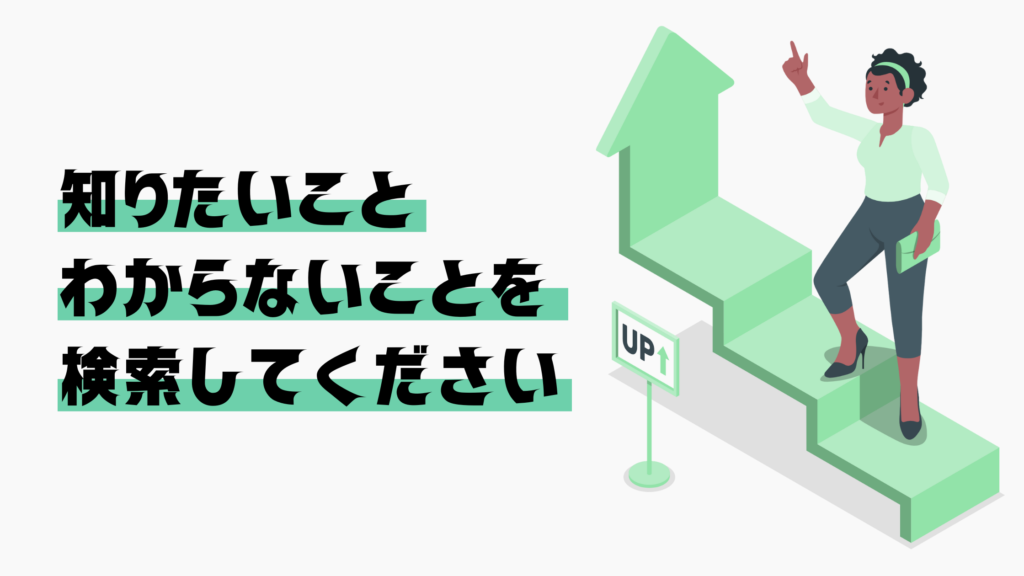


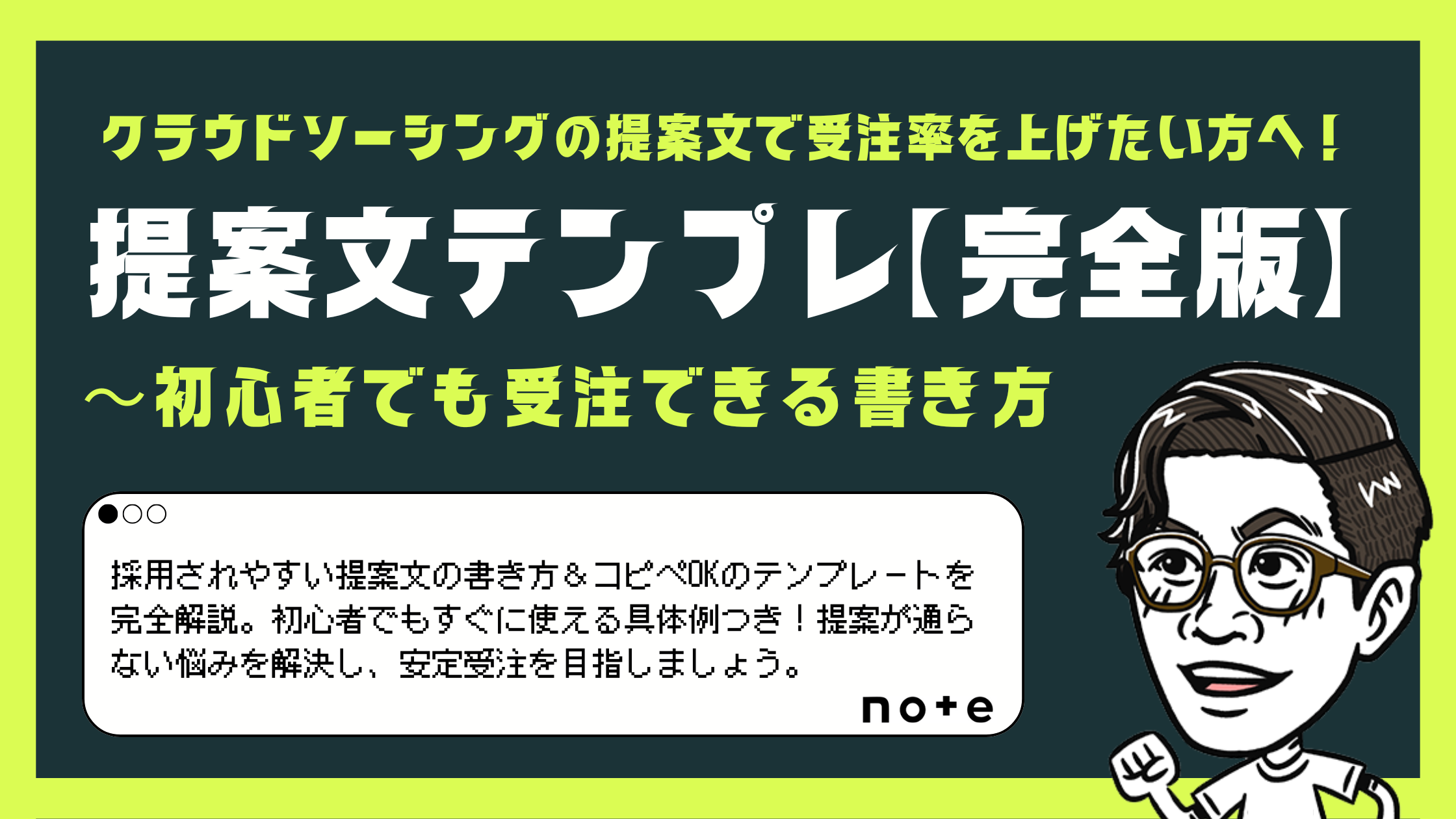


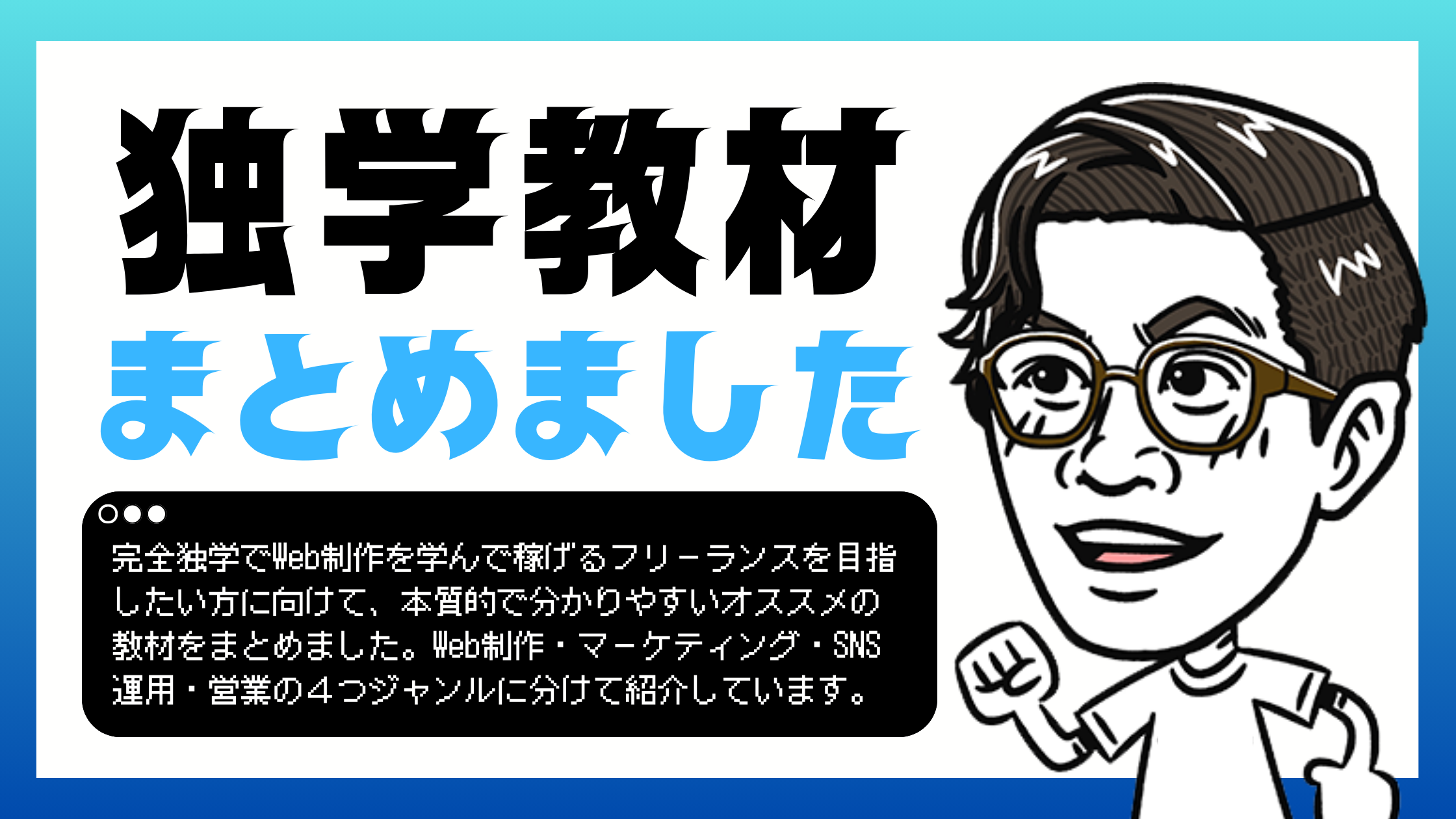
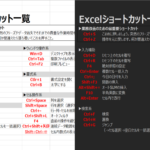
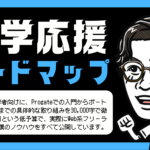
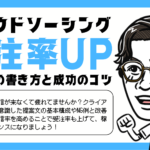
頑張ってコーディングを学んだけど、全然案件が取れない…