これを読んでくれているあなたは、きっとWeb制作などのスキルを身に着けて、副業で稼げるようになろうとしているはず。
そんな、あなたに質問です。
調子はどうですか?
思い通りに進まなくて焦ってませんか?
頑張りすぎて、挑戦開始から半年も経ってないのにメンタルをやられていませんか?
今回はそんな挑戦が上手く進まなくて悩んでいる人に向けて、メンターとして500回以上の面談と100人以上のサポートを経験してきた僕だからこそお伝えできる「正しい成功者マインド」について解説していきます。
前回の記事では、自分自身を嘘偽りなく勇気づけ、ありのままの自分を受け入れる方法について語りましたが、後編である当記事では、他者との健全な向き合い方を学び、人間関係を安定させる方法について語ります。
どんな挑戦も、自分と他者をそれぞれ正しく受け入れ、勇気づけられるようになる必要があるからです。
それでは、早速はじめましょう。
本記事の目次
①相手を勇気づけるために感謝を伝える

「前編」では、「正しいポジティブ思考」や「自己受容」の方法について解説し、自分を嘘偽りなく勇気づける方法を見てきました。
ここでいう「勇気」とは、困難を克服するための活力のこと。
つまり、「勇気がある」とは「自分は相手の役に立てるんだ!自分には価値があって、能力もあるんだ!」と思える状態のことでした。
未読の方はぜひ「前編」をご確認ください。
ここからは、視点を「自分」から「周囲」に変えていきます。
人間社会で常に明るく前向きに生きていくためには、自分だけでなく、周囲もポジティブにしていく必要がありますからね。
では、まず何をすればいいのか?
ここで登場するのが「感謝」です。
ありきたりすぎて拍子抜けしたかもしれませんが、「感謝」とは他者に対する強力な勇気づけのこと。
「ありがとう」の一言すらなかなか言えない人もいる世の中ですが、「〇〇さん、さっきは〜してくれて本当にありがとうございました!めっちゃ助かりました!」なんて言われたら、それだけで相手は「自分は相手の役に立てたんだ」と自己肯定感が高まるもの。
故に、これを繰り返し続けることで周囲の勇気づけを行い、チーム全体の空気を前向きに変えていけるんです。
また、この「感謝」とは相手をポジティブにするだけでなく、それを伝えている自分自身をもポジティブにする効果があります。
感謝を伝える側は「相手を勇気づけることで、相手の役に立っていること」を実感できるからです。
そもそも感謝の言葉を伝えるときに、怒ったり不機嫌そうな顔はしないですよね?笑
伝える側も伝えられる側も、みんなが優しくなれるのが「感謝」。
自分を勇気づけられるようになったら、今度は周囲を勇気づけることに挑戦してみよう!というお話でした。
②お互いの課題を分けて考える

前回は「自分だけでなく、周囲の人たちも勇気づけるために感謝を伝えていこう!」というお話でした。
相手を喜ばせることで自分も前向きになれるので、ぜひこれは毎日徹底していただきたいのですが、実はここにも挫折ポイントがあるんです。
それは「喜ばれない」ということ。
「お礼をしに行ったけど、相手の反応が薄かった」 「上司にお礼をしに行ったら、それを見てた先輩に嫌味を言われた」なんて経験、ありませんか?
こういうことが続くだんだん馬鹿らしくなってきて、仕舞いには感謝を伝える必要性が感じられなくなることもあるでしょう。
そこでご理解いただきたいのは、「別にそれでもいいじゃん」ということ。
相手がどう思うかは、相手の自由です。
どんなにこちらが工夫をしようと、相手の受け取り方をコントロールすることなんてできませんよね。
いわゆる「課題の分離」ってやつですが、自分にコントロールできないこと(定数)はどんなに悩んでも永久に解決しません。
それよりも、自分にできること(変数)に集中しましょう。
「チームの風通しを良くしたい」とか「助けてくれた人に感謝したい」と思ったのなら、損得を超えて実行するんです。
周囲の顔色を意識しすぎて、本意ではない行動を取るというのは「服従」しているようなもの。
そんな生き方では疲れるだけで、勇気を持つことも、周囲を勇気づけることもできないでしょう。
他人の期待に応えるために生きるのではなく、自分の人生を生きる。
人間関係の基本として、この考え方をご理解いただけたらと思います。
③自分の信念を貫くために異なる考えを受け入れる

前回は、自分がコントロールできないことで悩まず、自分が良いと思ったことを実行する大切さについて解説しました。
僕個人の経験からいっても、これを実践することでメンタルヘルスがかなり良好になるんですが、実はそこにもひとつだけ落とし穴が。
お互いに自分の考えを貫こうとした結果、意見が食い違ってしまった経験ってありませんか?

いや、「きのこ」じゃなくて「たけのこ」だ!
こうなってしまったときに、ただ意見をぶつけ合うだけでは物事は先に進みませんし、周囲の反応に合わせて自分の意見を曲げてしまうこともあるでしょう。
しかし、それでは本末転倒。
では、どうするか?
ここで利用すべきが「返報性の原理」です。
マーケティング関連の書籍でほぼ必ず出てくる原理ですが、これは人間関係を改善し、自分や周囲を勇気づけるためにも利用できるんです。
たとえば、先ほどのように意見が食い違っている場合をイメージしてみてください。
反対意見を述べている相手を「敵」とみなし、あなたが「反撃」したとしたら、相手も同じように受け止めて「反撃」してくるでしょう。
「返報性の原理」がネガティヴに働いているといえます。
一方、反対意見を述べている相手をあくまで「味方」とみなし、「自分とは異なる意見を発表している」と受け止めれば、それに「共感」した上でお互いの考えの違いについて冷静に話し合うことができます。
「返報性の原理」がポジティブに働いているわけですね。
「自分の信念を貫く」とは、決して他者の考えを根絶やしにしてでも自分の意見を押し通すことではありません。
仮に相手が喧嘩腰であったとしても、「たしかにそういう意見もありますよね」と反対意見に共感した上で、徹底して丁寧に議論を進め、互いの信念を尊重しながら建設的な議論に努めていきましょう。
「前編」でも述べたとおり、相手の反対意見にイラついてしまうことは決して悪いことではありません。
しかし、それは自分の本音として受け止めつつ相手の考えを尊重すると、相手に自分の考えを受け止めてもらえるようにできるというお話でした。
反対意見と衝突しがちな方や、ついつい周りに流されてしまいがちな方は、ぜひこれを意識してみてください。
④より大きな共同体の利益を優先する

ここまで「課題の分離」や「損得を超えた行動」、そして「信念の貫き方」について見てきました。
断言しますが、これらの考え方を実践できるようになれば、自分や周囲を勇気づけられる人となり、メンタルは安定し、挑戦し続けられるようになります。
しかし、それでもまだ不安になることはあるでしょう。
たとえば、みんなで話し合ったことが「本当に正しいことなのかな?」と疑問に思ったとき。
もしくは、あなたが転職を決意したものの「会社に迷惑を掛けちゃうかも…」と心配になったとき。
そんなときに思い出してほしいのは「より大きな共同体の利益を優先する」です。
自分たちにとっては有利な話でも、第三者目線で見たときに社会的な印象が悪いと思うなら、後者を優先した判断をすべきでしょう。
同じように、自分が転職することで現在の会社に迷惑を掛けてしまうとしても、あなたが転職先でこれまで以上に能力を発揮することでより多くの人の役に立てるなら、転職すべきです。
もちろんあなたの決断をすべての人が好意的に捉えるわけではありませんが、以前にも書いたとおり、他者がどう思うかはコントロール不可能。
心無い言葉をかけられて傷つくこともあるかもしれませんし、想像以上に辛い想いをするかもしれません。
しかし、それらすべてを受け止めた上で自分の決断を貫くことが、結果的に自分を勇気づけ、挑戦を続けるモチベーションにつながるというお話でした。
ちなみに、ここまでを読んでこう思った人がいるかもしれません。
「より大きな共同体の利益を優先した結果、自分のチームに損失を出すなど迷惑を掛けてしまったら、みんなから嫌われるんじゃないですか?」と。
次回はそんなケースの対応方法についてお話ししようと思います。
⑤「信用」と「信頼」の違いを理解する

この記事も終盤に突入しましたので、ここまでをザッと振り返ってみましょう。
まずは、「前編」で自分自身を正確に評価して、無条件で受け入れるための考え方について解説しました。
それらを実践することが、精神を安定させて目標に向かって毎日挑戦できる基礎になるわけですが、自分の挑戦を成功させるためには自分が前向きになるだけでは不十分。
日々の生活においては、他者との関わり方にも工夫が必要ですからね。
そこで、「後編」では前回までにあなたの人間関係を良好にして、それを維持するために必要な考え方について解説してきました。
「課題の分離」、「損得を超えた行動」、「信念の貫き方」、そして「判断に迷ったときに優先すべき基準」についても解説してきたわけですが、このテーマでお話しするのも残すところあと2回。
ということで、ようやく本題なのですが、今日の内容は前回の最後に予告したとおり。
「より大きな共同体の利益を優先した結果、自分のチームに損失を出すなど迷惑を掛けてしまったら、みんなから嫌われるんじゃないですか?」という疑問に答えます。
答えは単純明快。
「人には優しく、自分には厳しく」です。
人間関係は「信頼」で成り立っているので、良好な人間関係を築きたいなら超優秀な人から超アホな人までみーんな引っくるめて仲間として捉え、たとえ裏切られても常に可能性を信じることが大切です。
家族との関係性がまさにこれですね。
子どもがグレて万引きしたとしても、親子の縁を切る人は少ないでしょう。
一方で、組織というのは「信用」の積み重ねで成り立っているものなので、結果を出さなければ評価されませんし、裏切られれば信じてもらえなくなります。
自分の信念に基づいてより大きな共同体の利益を優先し、自分のチームに不利益を与えるような迷惑を掛けたのなら、人としての判断が正しくても、チームの一員としては評価されなくて当然。
仮に上司が評価をつけるときに「こいつは世のため人のために身を投げ出せるすごい奴なんだよな」と思いながらも、評価を低くつけたとしたらそれは組織の評価者という立場を正しく理解している妥当な判断なんです。
「前編」であなたの「存在価値」と「能力価値」は別物だという話をしましたが、それと同じように「信用」と「信頼」もまた別物。
このことを理解できると、職場という「信用」で成り立つ組織の中でもモチベーションを管理しやすくなるでしょう。
組織の一員として働く方はもちろん、フリーランスとしてクライアントや外注先の人々と関わる方にとっても、ここは十分にご理解いただきたいところです。
⑥任せることで相手を勇気づける

前回は「信用と信頼は別物」というお話をしましたが、チームで仕事に取り組むときにもうひとつ大切なことがあります。
それが「任せる」ということ。
そもそも仕事に慣れてくると「あれもこれも自分でやる方が早い」と思ってしまいがち。
しかし、それではチームとして成長できませんし、仲間との信頼を深められません。
当然、「任せる」というのは誰に何をどの程度任せるのか?というのがポイントになりますが、今日ここで理解してほしいのは、そもそもあなたは他者を頼っていいんだということ。
他者を信じ、頼って、甘えて、感謝してください。
フリーランスだろうと、会社員だろうと、ここは同じです。
逆に相手目線で考えると、任せられるというのは「信頼されているんだ」と勇気づけられることであり、その勇気が次の成長へと大きく影響します。
きっとあなたも過去に何かを任され、それに挑戦する中で成長してきたはず。
そのときと同じように、あなたも相手を信じて、頼ることで、より良い仕事を実現してもらえたらと思います。
僕はWeb制作の初心者向けに《独学応援サロン》という無料のコミュニティを運営していますが、それは自分がフリーランスとして仕事を続ける中で「初心者にこそそういう信じられる人たちとの出会いが必要不可欠だ」と思ったことがきっかけでした。
ちなみに、他者を頼って任せたとして、そのあと誉めようとする人がいますが、それだと逆効果になることがあるのでご注意を。
日頃の関係性や言い方次第ですが、「あいつ、自分では何もしないくせに偉そうにしやがって」と思われてしまうケースも珍しくありませんからね。
「褒める」のではなく「感謝する」。
これを意識していただき、常に関係性がフラットなることを重視してもらえると、「任せる」の効果を最大限に活かせるでしょう。
日々の挑戦を成功させるために、自分を勇気づけ、周囲も勇気づけられるようになることの大切さをご理解いただけていたら幸いです。
おわりに 〜対人スキルに不安のあるあなたへ

以上が、他者との健全な向き合い方を学び、人間関係を安定させる方法でした。
さて、さいごにここまでを総括しましょう。
「僕たちが挑戦を成功させるためにやるべきこと」をまとめるとこうなります????
「勇気」によって自分たちの活動性を高め、「共同体感覚」を実践していく。
「前編」では自分を勇気づける方法について解説し、「後編」となる本記事では共同体感覚について解説しましたが、このふたつのキーワードこそが、僕たちを幸福な人生をへと誘う両輪となってくれるということです。
このことを「Web系フリーランスを目指す」という切り口で考えてみましょう。
この章を書いているときに、Xでちょうどこんなポストを見掛けました。
Web系フリーランスを目指したいという方の多くは、対人コミュニケーションをできるだけ避けるためにその道を選ぶことが多いです。
たしかに、フリーランスのデザイナーやコーダーって接客業などに比べると他者とのコミュニケーションは少ない職業です。
しかし、少ないとはいえゼロではありません。
ゼロではないのでコミュニケーション能力は必要ですし、僕がこれまでに見てきた「活躍しているフリーランス」の方ほどコミュニケーション能力は総じて高かったです。
そのため、対人スキルの低い方はそれ以外の要素で競合たちを圧倒する実力を示さないと仕事を勝ち取るのは難しいでしょう。
しかし、百戦錬磨の超ベテランならいざ知らず、このブログを読んでくれているあなたはきっと初学者ですよね?
だとすれば、人間関係を安定させる方法を知り、実践することが、デザインやコーディングの技術を学ぶことと同じくらい重要であることをご理解いただけるのではないでしょうか?
まずは、成功者たちに共通している正しい自己受容の方法を解説した前編を参考に、自分自身を嘘偽りなく勇気づけ、ありのままの自分を受け入れられるようになってください。
それをクリアできたら、今度はさまざまな人間関係をシンプルにするための方法を解説した「後編」を参考に、他者との健全な向き合い方を学び、人間関係を安定させる方法をご理解いただき、今後の生活の中で実践していただければと思います。
《独学応援ブログ》ではWeb制作の独学や営業で重要な心構えやテクニックを数多くお伝えしていますが、それらの根本に必要な考え方が今回の2本の記事で解説したものです。
ぜひ対人スキルに不安のある方や、まさにいま周囲との人間関係に悩んでいるという方にご参考いただけると嬉しいです。
感想や質問などございましたら、いつでもXや《独学応援サロン》にてご連絡ください。
それでは、今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
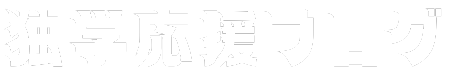
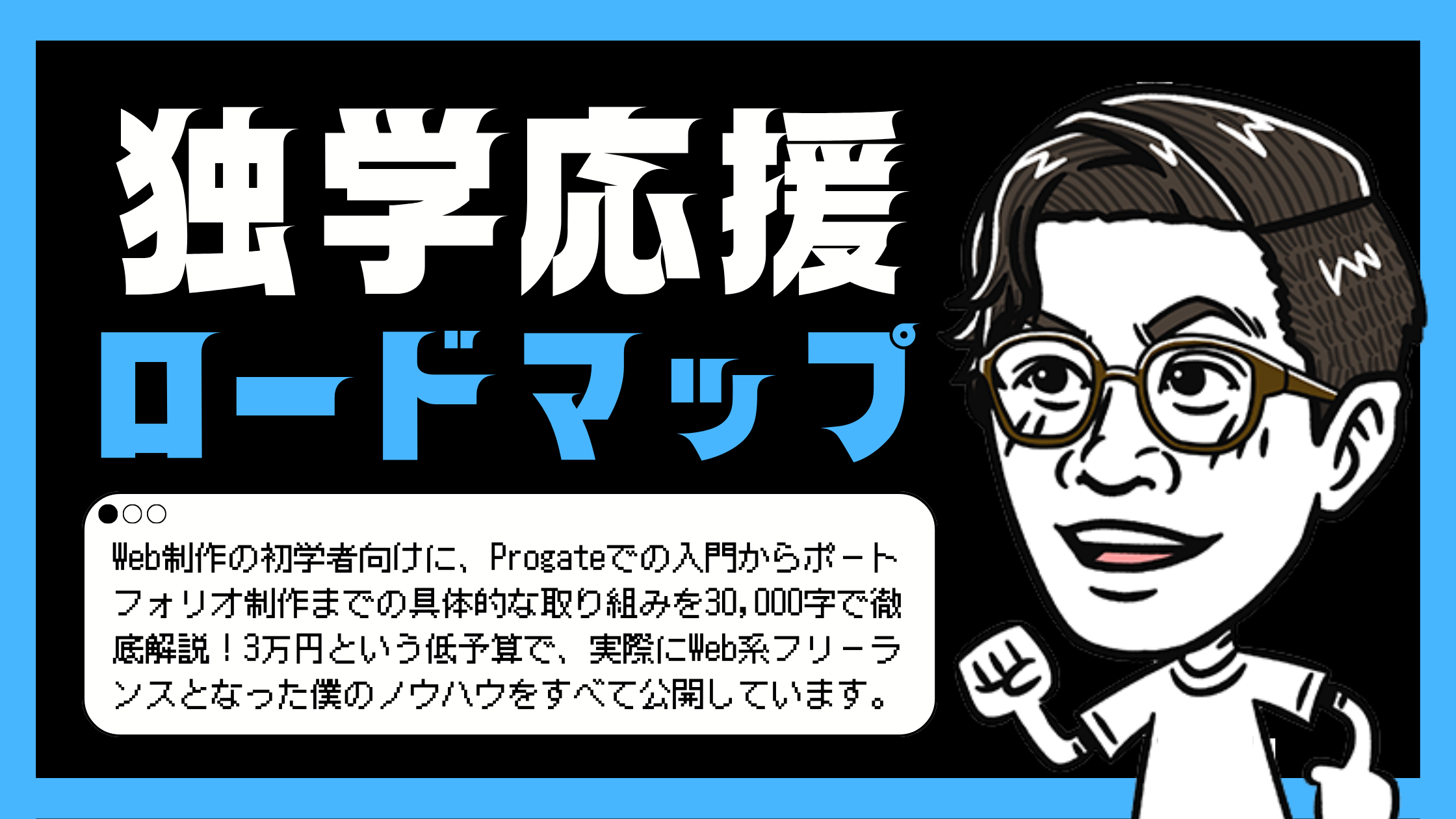

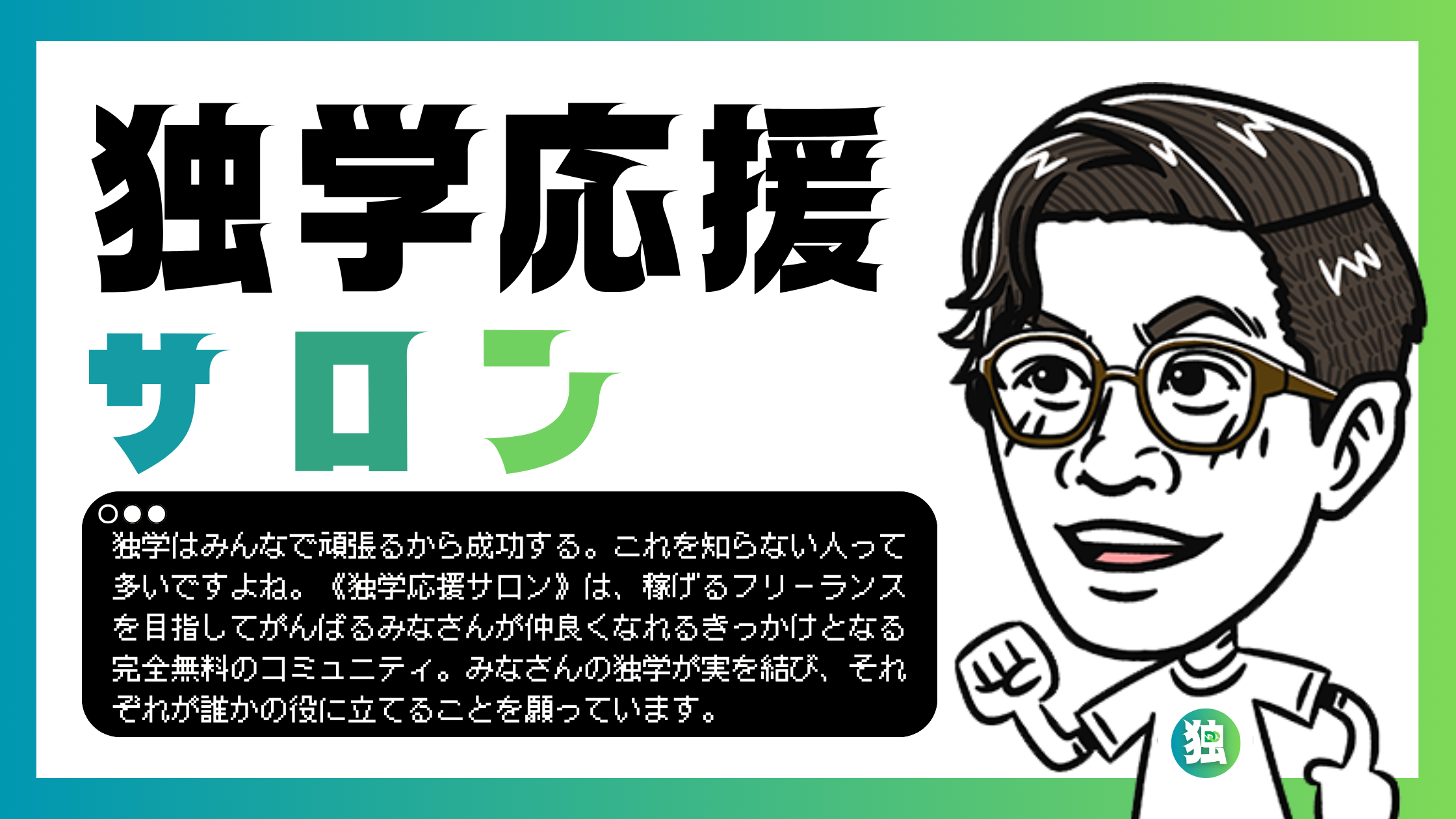

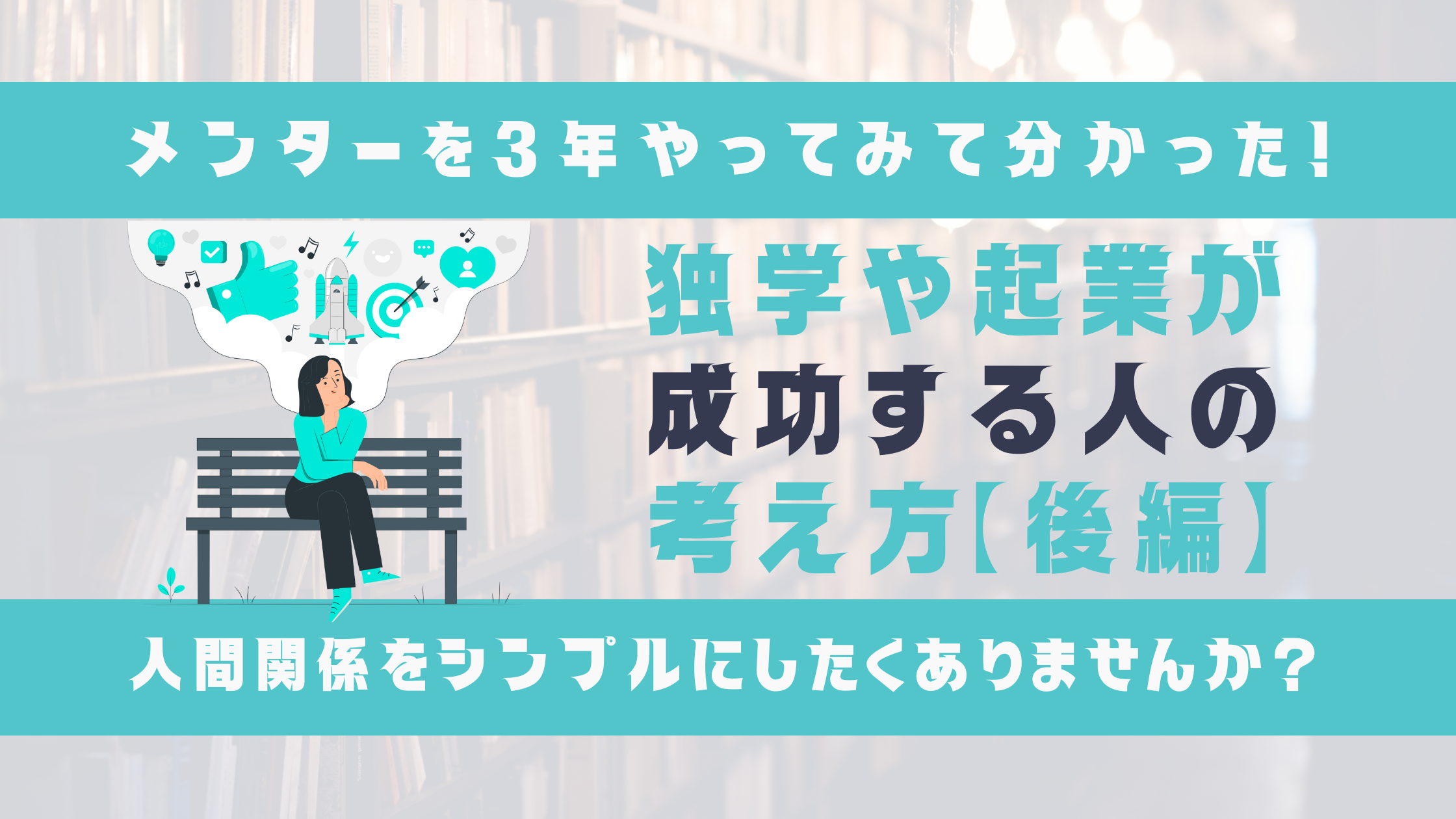
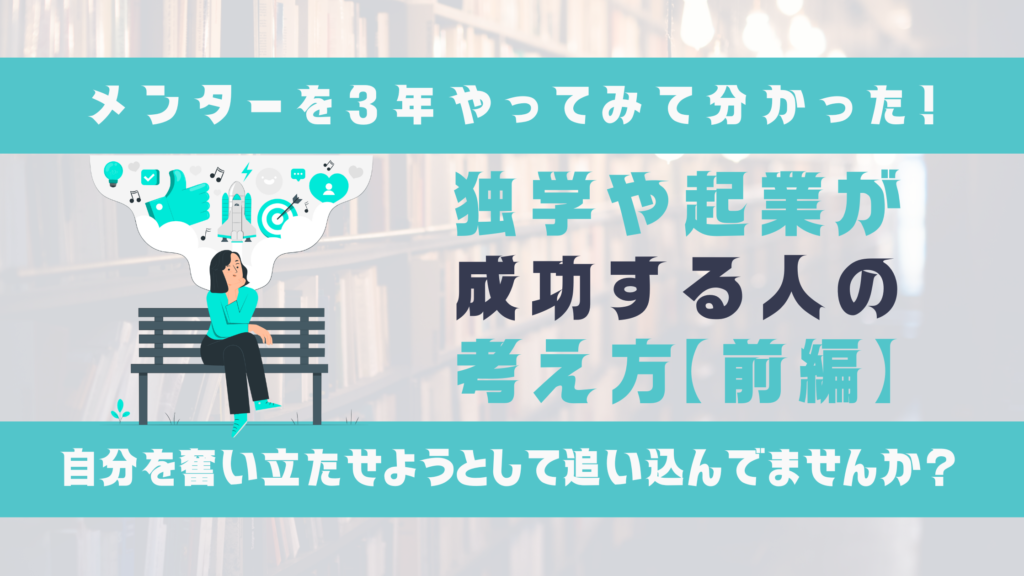
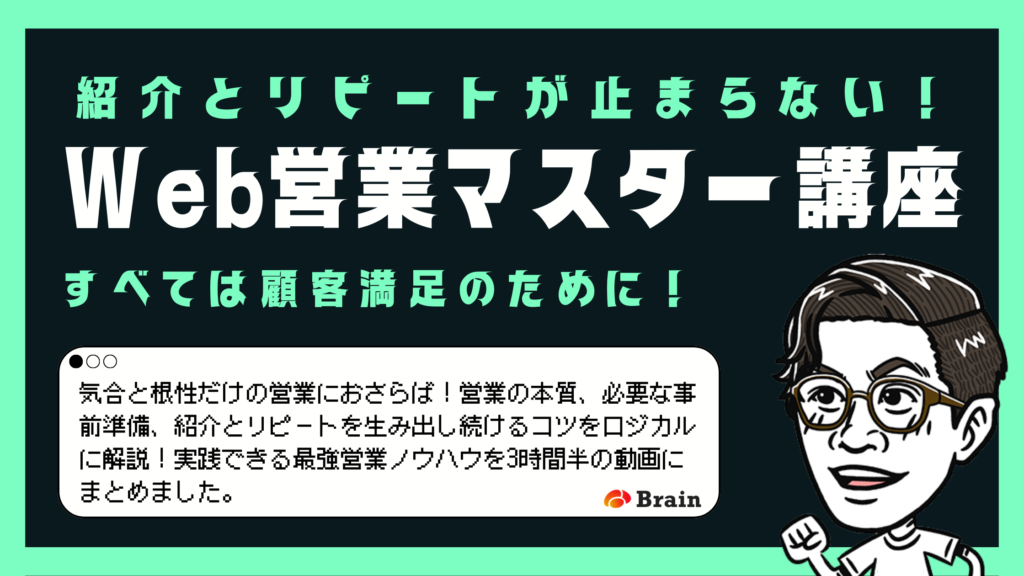
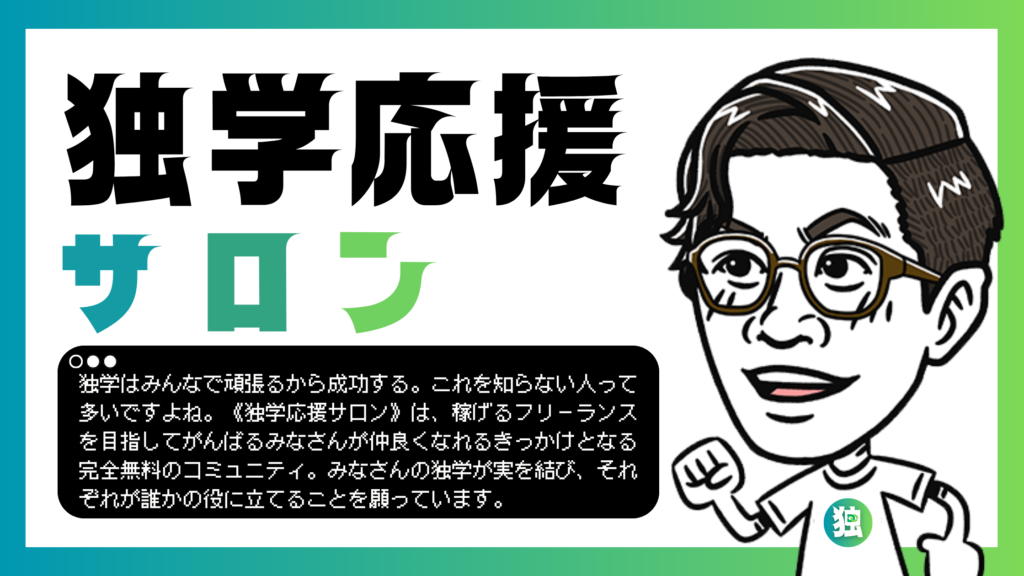

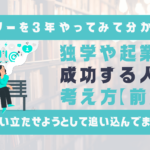

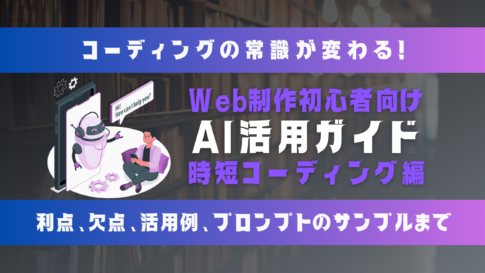
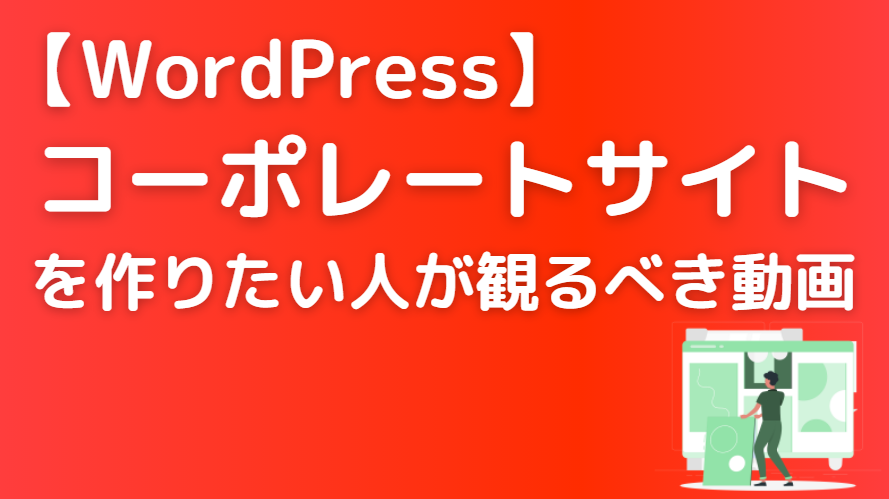
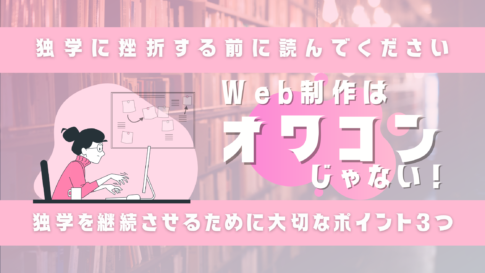
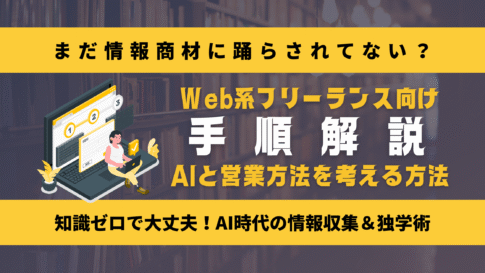
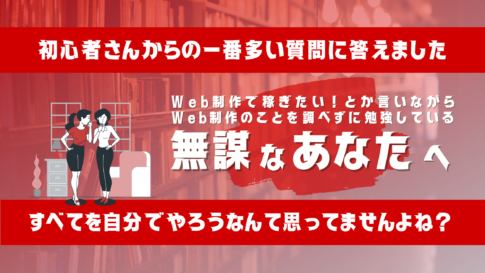
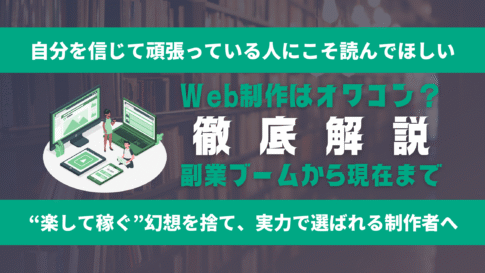
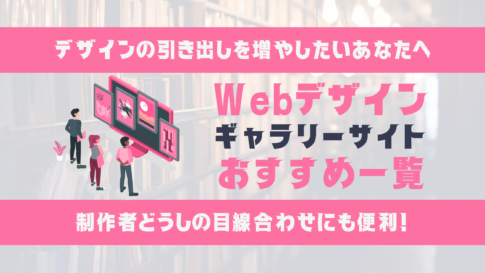
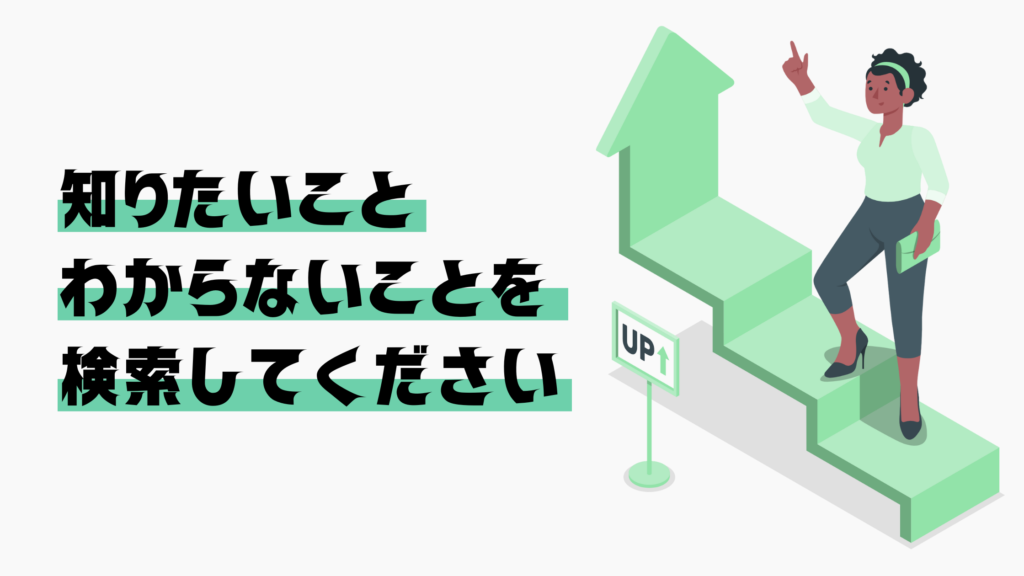

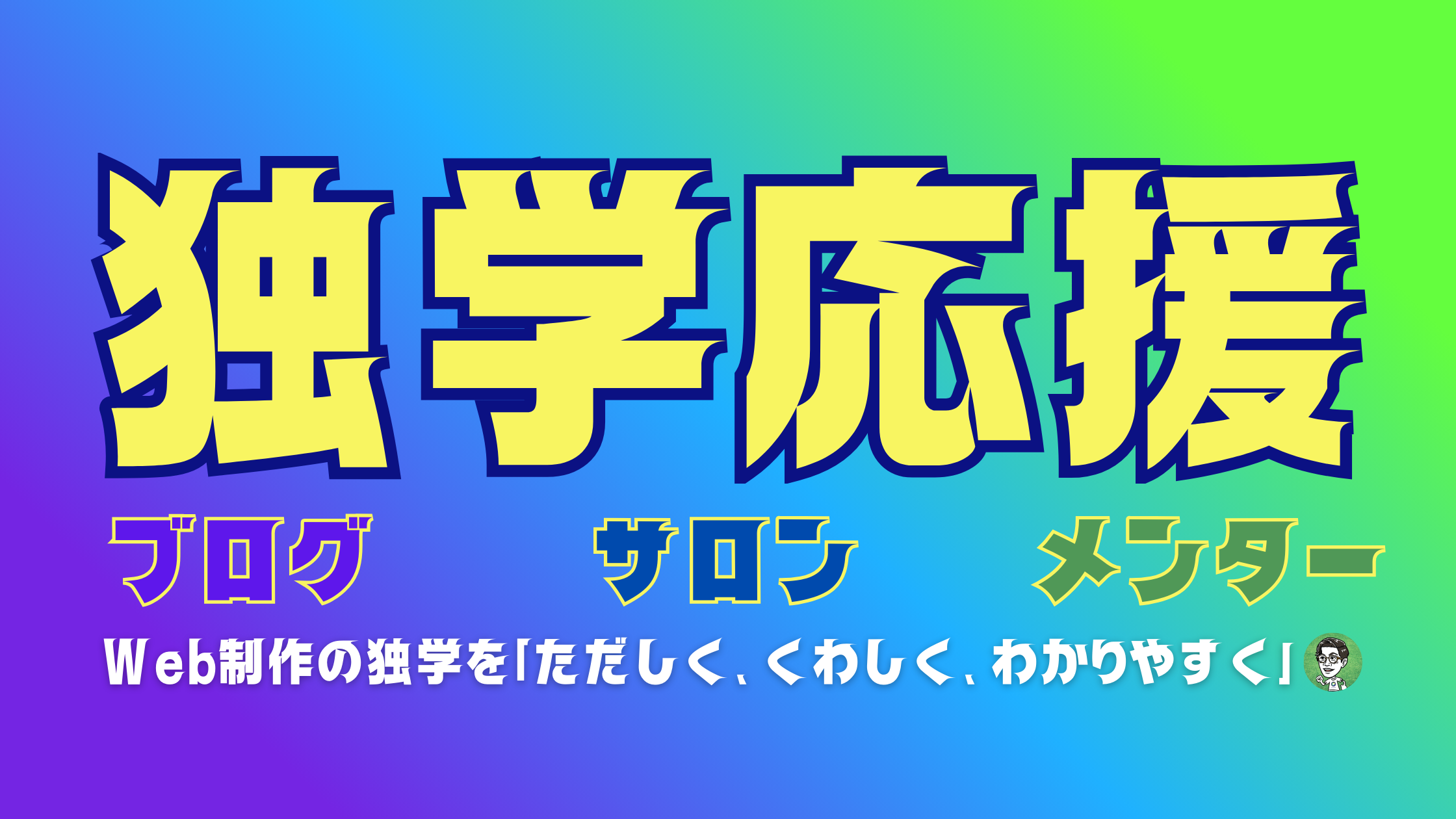
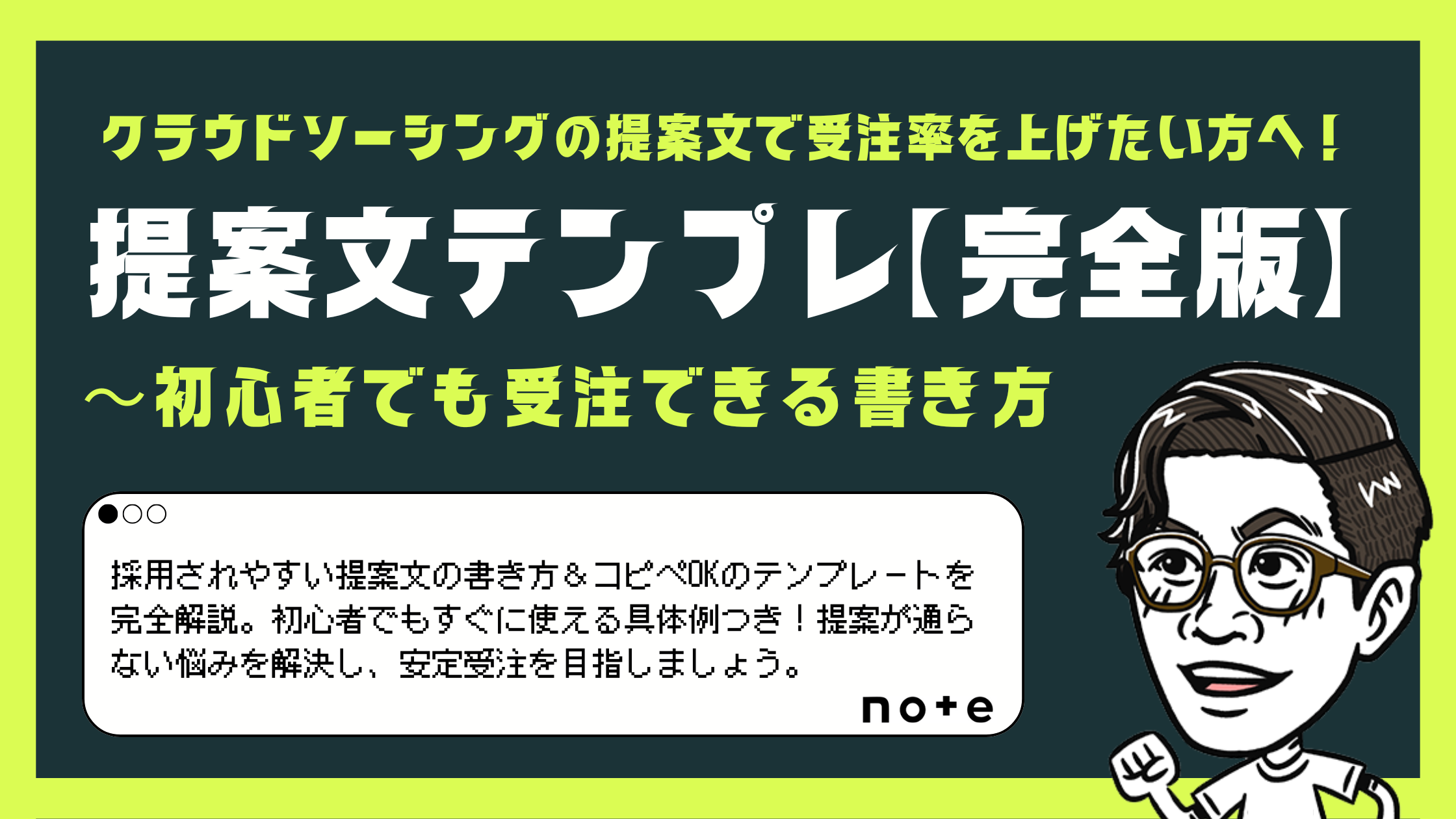


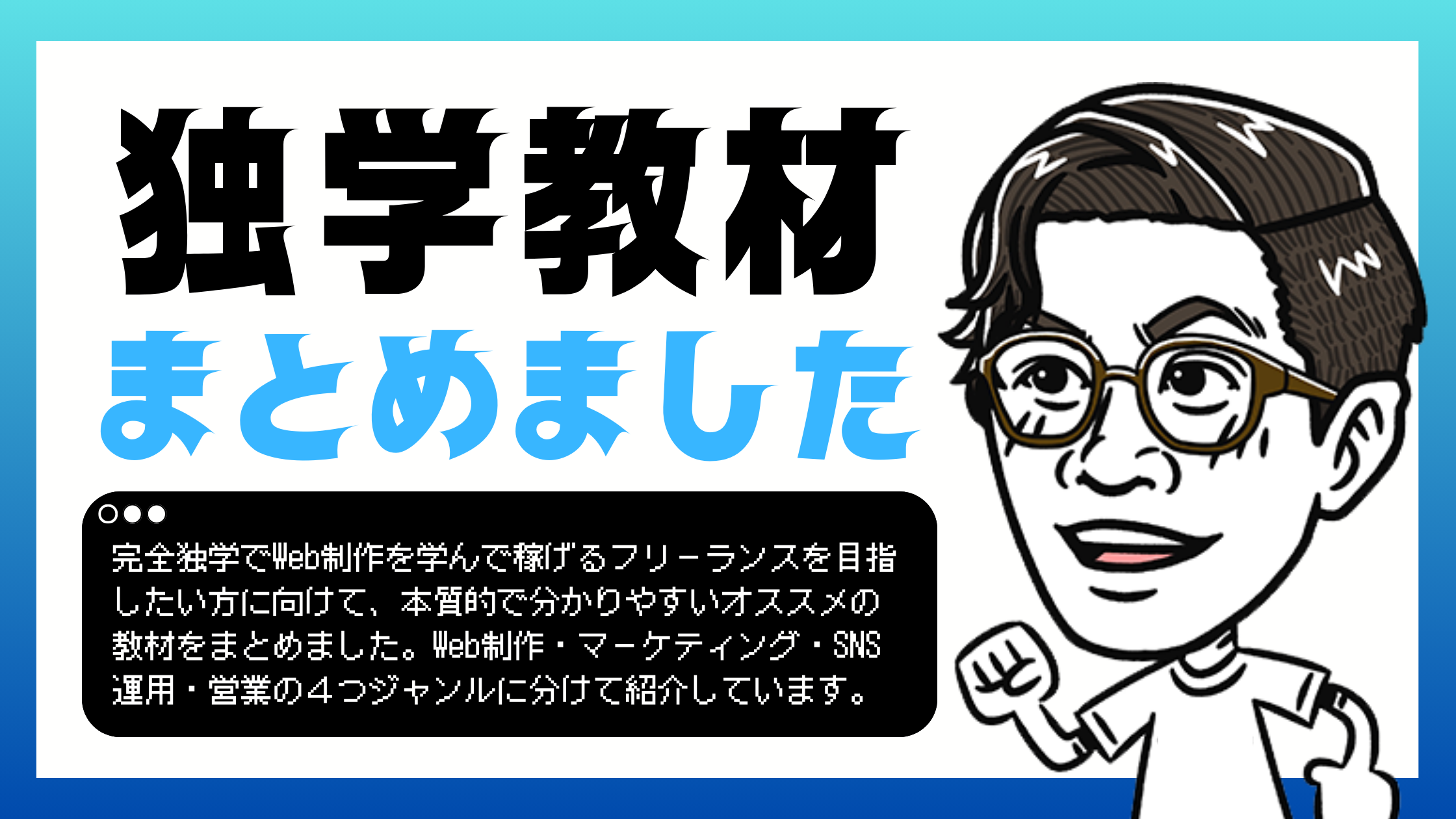
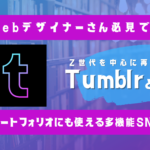
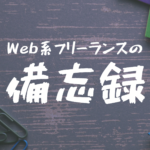
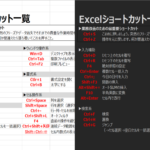
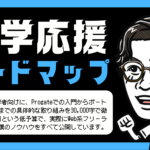
いちばん人気なのは「たけのこ」じゃなくて、「きのこ」だ!